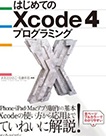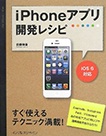「リンク格差社会 ~ウェブ新時代の勝ち組と負け組の条件」を読んだ
公開日:
:
最終更新日:2014/01/30
本
記事内に広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
以下、レバレッジメモ。

リンク格差社会 ~ウェブ新時代の勝ち組と負け組の条件~ (マイコミ新書)
- 作者: 江下雅之
- 出版社/メーカー: 毎日コミュニケーションズ
- 発売日: 2007/08/10
- メディア: 新書
- 購入: 1人 クリック: 15回
- この商品を含むブログ (15件) を見る
p.19
インターネットの独自性は「つなぐ」機能にあるのではないか。
p.23
アマゾンの場合、消費者自らが売れ筋を並べてくれるようなものである。
p.26
1日平均取扱高は19億円以上
ヤフオクに関するデータ。
p.34
インターネットなら人目を気にすることがない。
アダルトサイトに関する言及。
p.53
情報というものは、本来、お互いに関連し合ってこそ価値があるといえる。
p.56
1つの関心事を軸に、広告を見せたい人、広告に関連するウェブを見せている人、そこにアクセスして広告をクリックしそうな人を媒介するという役割なのである。
Googleについて。
p.58
ユーチューブもまた、リンクの連鎖をもたらす。
p.78
私論の連鎖がパワーとなる
p.89
携帯電話のアドレス帳には、持ち主の人間関係が可視化されている。
p.100
歴史上いま初めて、科学者たちは、あらゆる種類のネットワークの構造について有意義に論じる方法を学びはじめ、以前は何も見つけることができなかったところにも重要なパターンと規則性が存在することに気づきだした
p.106
ウェブの背後にあるネットワークでは、少数のリンクしかもたない地味なサイトが、莫大なリンクをもつ少数のウェブサイトによってつなぎあわされているのである。
p.109
有名であればあるほど、より多くのリンクを獲得する
p.132
グーグルは世界中のウェブ情報を網羅的に収集することによって、アマゾンはユーザーから記述投稿されるレビューなどを利用することによって、自社サービスを充実させてきた。
p.137
ロングテールの法則が成立する条件は、ほしがる人がほとんどいないようなモノを売りたい人と、普通なら誰もほしがりそうにないモノを買いたい人との出会いが生じ、きわめてまれな組み合わせのリンクが形成されることだ。
p.143
リワイヤリングはネットワークを多重構造にする。通常のチャンネルが機能する一方で、別のトポロジーを持つネットワークが重ね合わされる。
p.146
大衆化された複製技術はしかし、マスメディアとは異なるメカニズムで影響力を発揮する。
p.150
私たちはすでに、膨大な生活記録(ライフログ)をインターネットに残している。
p.172
マイミクシィの多さがコミュニケーションの活発さを単純に示すわけではないのだ。
p.202
コネクターとはクラスター間をつなぐ役である。
メイブンとは、事情通、情報通と評される人だ。
p.203
セールスマンとは強い説得力の持ち主で、他者に「感染」させる術に長けている。
p.206
さながら、ひとつの「論壇」とでも言うべき様相を呈しているものもある
はてなブックマークに関して。
p.213
知人コレクターになるなかれ。日常的な活動のなかで接点を持てる人、問題意識を共有できる人とのネットワーク化を志向すること
p.234
パブリックビューを観に行けば、そこで同類との「つながり」を味わうことができる。結局、その感覚が最大の魅力であるからこそ、人は集うのである。