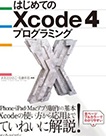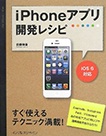デジタルネイティブの時代
公開日:
:
最終更新日:2013/11/05
書評
記事内に広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
デジタルネイティブに関してあまり詳しくないので、この本を入手して読んでみた。
以下、目次
第1章 増殖する「デジタルネイティブ」(3歳の息子の口ぐせ
ネイティブとノンネイティブの埋められない溝 ほか)
第2章 「ノンネイティブ」たちが今気付かなければならないこと(ノンネイティブも経験してきた文化の変遷
流行りの「クラウドコンピューティング」はビデオの登場と同じ ほか)
第3章 インフラの発展が意味すること(デジタルネイティブがビジネスの本流になる時代
ライフスタイルに革命を起こした「インフラ」の発展 ほか)
第4章 デジタルネイティブを生み出したビジネス巧者たち(「つながり」と「情報収集」がキーワード
デジタルネイティブにやられる既存メディア ほか)
第5章 ネットでビジネスを劇的に変える(マイノリティになるノンネイティブ
普遍的な「ビジネスの本質」とは ほか)
主に国内のデジタルネイティブについて焦点が合わされている気がする。国内のデジタルネイティブについて幅広く取り上げられているので、例えばケータイサイトなどに携わりたい方は読んでみると得るものがあるかもしれない。
以下、気になった部分から引用。
「ノンネイティブ」にももちろん「五人組」という意識はありますが、それが会社などの組織の前では「百人組」や「千人組」といった形でとらえようとします。ところが「デジタルネイティブ」は、「五人組」を10個、20個と持っていて、そのひとつに会社があると位置づけています。つまり、会社がすべてではなく、会社も自分が複数持つ「五人組」のひとつに過ぎないと言えます。
むしろ、「ニッチ」をしっかりと攻め、結果として「マス」になっていくことを考えていかなければならないのが、ネットマーケティングの極意と言えるでしょう。
社員がどんどん外に向かっていくことを許容してあげられる会社でなければ、「デジタルネイティブの時代」に勝ち残ることはできなくなってしまいます。企業側にも社員の「発信」を認める姿勢が必要なのです。
ところが、「デジタルネイティブ」にとっては、そのような出世レースよりも誰かとつながっていることのほうがモチベーションが上がることがあります。出世をしても、仕事が忙しくなり、自分の時間がとれなくなるということを、決して「出世」したと思われなくなるのではないでしょうか。
そして、その発信のカギを握るのは「映像」と「ケータイ」にある。それが本書の結論です。
消費者も社員も取引先の担当者もデジタルネイティブになっていくのだから、彼らのことを「よくわからない、理解できない」というだけではなく、対応方法をきちんと考えていかないと破綻してしまうでしょうね。
関連記事
- PREV
- 目に優しいディスプレイについて
- NEXT
- 寺山修司「書を捨てよ、町へ出よう」